今日はですね、「読んで良かった心に響く最強本・海外編」を紹介したいと思います。いやぁ……これがまた面白かった。ページをめくる手が止まらない。気づけば夜中の2時。翌朝「やっちまったなぁ」って顔でコーヒー飲んでるわけですよ。
本って、たまにありますよね。「ああ、これ読んで良かったなぁ……」って心にズシンと残るやつ。今回は、そんな海外小説たちをまとめてご紹介します。
- 読んで良かった!心に響く 最強の海外本 【海外編】
- 『相続ゲーム エイブリーと億万長者の謎の遺言』ジェニファー・リン・バーンズ 2025/7/24新刊
- 『私立探偵マニー・ムーン』リチャード・デミング 2025/6/25新刊
- 『密やかな炎』セレステ・イング 2025/5/9新刊
- 『死者は嘘をつかない』スティーヴン・キング
- 『女彫刻家』【新装版】ミネット・ウォルターズ 2024/5/31
- 『五月 その他の短篇』アリ・スミス 2023/3/24
- 『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド 2022/10/28
- 『スクイズ・プレー』ポール・ベンジャミン 2022/8/29
- 『ダーク・ヴァネッサ』ケイト・エリザベス・ラッセル 2022/5/3
- 『短くて恐ろしいフィルの時代』 ジョージ・ソーンダーズ 2021/8/5
- 『瞳の奥に』サラ・ピンバラ 2021/2/28
- 『ブルックリン・フォリーズ』ポール・オースター 2020/5/28
- 『ジーヴズの事件簿 才智縦横の巻』P.G. ウッドハウス 2011/5/10
- 『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』 ジェレミー・マーサー 2010/5/13
- 『ずっとお城で暮らしてる』シャーリィ・ジャクスン
- 『愛のゆくえ』リチャード ブローティガン 2002/8/1
- まとめ
読んで良かった!心に響く 最強の海外本 【海外編】
『相続ゲーム エイブリーと億万長者の謎の遺言』ジェニファー・リン・バーンズ 2025/7/24新刊
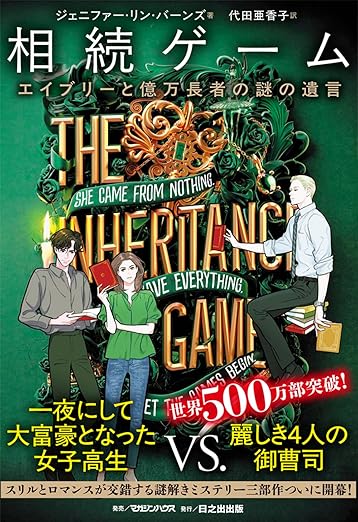
これね……読んでて思い出しました。「ハリー・ポッター」とか「ハウルの動く城」読んだときのワクワク感。秘密の通路や謎だらけの大豪邸。そこで暮らす条件付きの遺産相続って設定だけで、もう心が躍ります。
エイブリーって普通の女子高生なんですよ。母親を亡くして、父親はどこにいるか分からない。奨学金のために必死に勉強してた子が、突然「大富豪の遺産を全部あげる」って言われちゃう。人生ひっくり返るでしょ、これ。
しかも屋敷に仕掛けられた暗号を解くシーンなんて、「ダ・ヴィンチ・コード」ばりのスリル感。読んでるうちに、自分まで謎解きに参加してる気分になるんですよ。
印象的だったのは、四人の御曹司たちとの駆け引き。敵なのか味方なのか分からない、その微妙な関係性がドキドキを加速させてくる。海外YA小説ってやっぱりこういう「青春とスリルの融合」が上手いなぁと感じました。
『私立探偵マニー・ムーン』リチャード・デミング 2025/6/25新刊
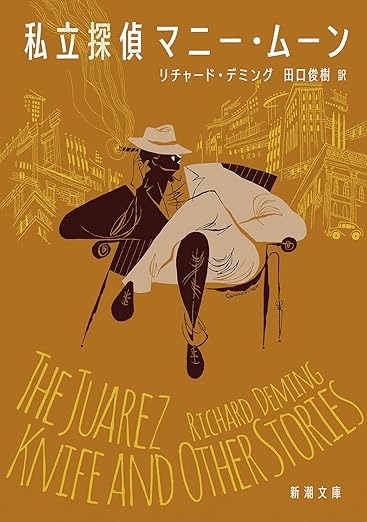
正統派のハードボイルド探偵小説なんですけど、実はこれ1940年代に書かれてるんです。驚きですよね。主人公は義足の探偵マニー・ムーン。義足っていうだけで、すでにキャラ立ちしてる。
冒頭からテンポがいいんですよ。依頼人の弁護士に呼び出されて事務所に行ったら、いきなり殺されてるんです。「おいおい、待ってくれよ!」って、ページめくる手が止まらない。
で、マニー・ムーンがまた洒落たセリフを吐くんですよ。これがカッコいい。ハードボイルドっていうと渋いオッサンの煙草の煙みたいなイメージあると思うんですけど、ここにはちゃんと本格的な「謎解き」の要素もあって、ラストに関係者を集めて推理を披露する王道スタイル。これがもう最高。
読後、「こういう高品質のB級映画風作品って、いいなぁ」って思いました。心にずっと残るわけじゃないんだけど、その瞬間、最高に楽しい。映画でいうと『ダイ・ハード』観終わった後の爽快感に似てます。
『密やかな炎』セレステ・イング 2025/5/9新刊
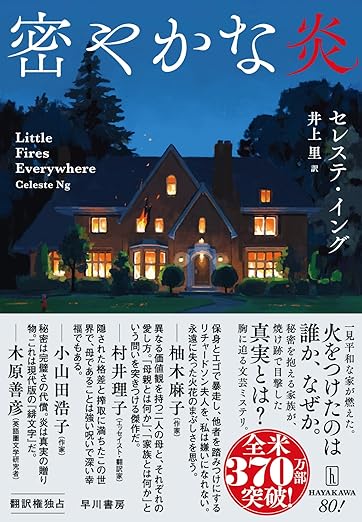
これね、読んでて何度も立ち止まっちゃいました。1998年のオハイオ州、リチャードソン家っていう「完璧な家庭」が舞台。で、その家がいきなり燃えちゃう。しかも「家族それぞれの部屋に火をつけた跡がある」っていう不穏な幕開け。
一番心に残ったのは、反抗的な末娘イジーと、芸術家ミアとの関係。自由を愛する二人が、規律と体裁を守りたい母親エレナとぶつかるんです。この対立が痛いほどリアル。
「自分らしく生きたい」って気持ちと、「社会の枠に収まらなきゃ」ってプレッシャー。その間で揺れる葛藤って、多かれ少なかれ誰にでもありますよね。
ドラマ化もされてるんですけど、小説を読むと「火をつけたのは誰か?」っていうミステリー以上に、「自分はどう生きたいのか?」って問いが胸に突き刺さるんですよ。
『死者は嘘をつかない』スティーヴン・キング
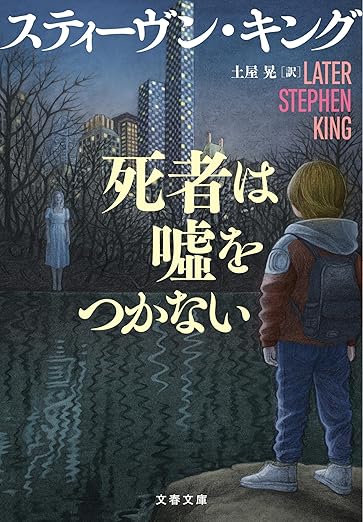
出ましたキング先生。今回もやっぱり外さない。死者が見える少年ジェイミーの話なんですけど、「死者は嘘をつけない」って設定がめちゃくちゃ面白い。
ジェイミーは自分の力を積極的に使おうとしないんですよ。そこが逆にリアルでいい。だけど、大人たちが「その能力、利用できるんじゃね?」って近づいてきて、どんどん事件に巻き込まれていく。
一番ゾッとしたのはラスト。死者が嘘をつけないからこそ、知りたくない真実が浮かび上がるんです。これね、「真実って本当に必要なの?」って考えさせられました。ホラーだけど、青春小説でもある。不思議な読後感でしたね。
『女彫刻家』【新装版】ミネット・ウォルターズ 2024/5/31
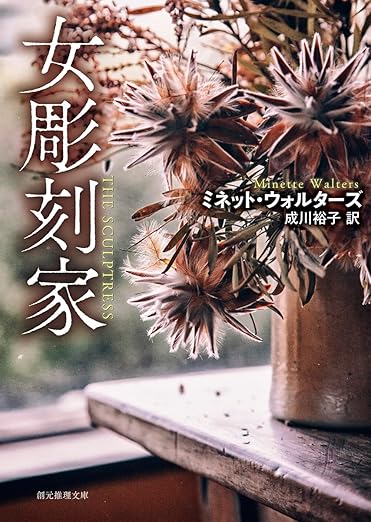
最初からインパクトが強烈すぎる……。母親と妹を切り刻んで、また人間の形に並べるなんて。しかも、台所の床に血で抽象画。これ、ちょっとホラー的でもありますよね。
でもこの作品の恐ろしいところは「精神鑑定で正常」って結果が出ちゃうところなんです。つまり彼女は狂ってない。なのに、なぜそんなことをしたのか。しかも罪を認めて弁護もしない。
孤立した家庭環境や周囲からの嫌悪感が、“彼女が犯人であることを誰も疑わない”という状況を作り出していて、そこに社会の冷たさが滲むんですよ。読みながら「いや、本当に彼女がやったのか?」と疑わざるを得なくなる。ミステリとしても心理劇としても、めちゃめちゃ気になる一冊です。
『五月 その他の短篇』アリ・スミス 2023/3/24
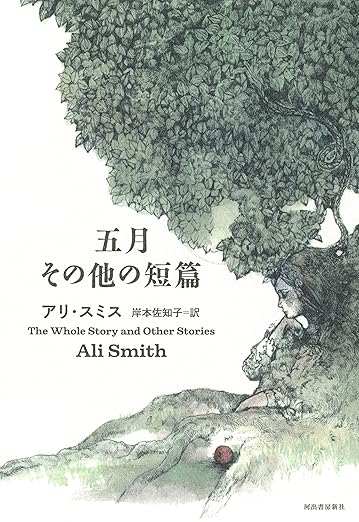
この短篇集、ほんとに不思議。木に恋する女性とか、他人に見えないバグパイプ楽隊に付きまとわれる老女とか、もう現実と幻想の境目がふにゃっと溶けちゃうような世界。
読んでて「この人の頭の中には、どれだけ奇妙で魅力的な人たちが住んでるんだ?」って本気で思います。しかも、ただの不思議話じゃなくて、ちょっと切なくて、ちょっと笑えて、読み終わったあとに「おかしいって言われても、私は私でいいじゃん」って思わせてくれるんですよね。
『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド 2022/10/28
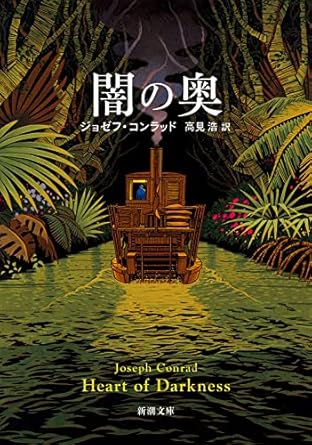
この作品を語るとき、やっぱり映画『地獄の黙示録』の影響が強いんですけど……舞台はカンボジアじゃなくてアフリカ・コンゴ。文明社会から隔絶された大地を遡っていく物語は、まさに“人間の奥底に潜む闇”を直視させられる体験です。
正直ね、読みながら「ちょっと難しいな」って思う瞬間もあるんですよ。でも解説を読むと「ああ、これは文明を飲み込む自然の魔性の話なんだ」と腹落ちする。
名作ってこういうことなんだろうな、と。読むたびに新しい解釈が生まれる。
『スクイズ・プレー』ポール・ベンジャミン 2022/8/29
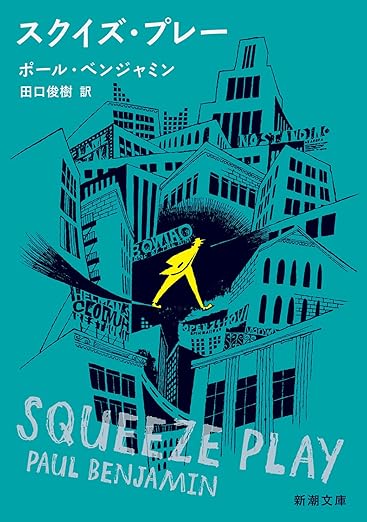
これぞハードボイルド!私立探偵マックス・クライン、危険の連続、依頼は脅迫事件、裏に潜む過去の事故……もうテンプレ満載なんですけど、その“王道感”が逆に最高なんです。
しかも途中で野球観戦の場面があるんですが、そこにオースターの人生とリンクするような影が差す。娯楽小説なのに、不条理な現実が静かに重なって見えてくるんですよね。
ハードボイルドに酔いしれたい人はぜひ。
『ダーク・ヴァネッサ』ケイト・エリザベス・ラッセル 2022/5/3
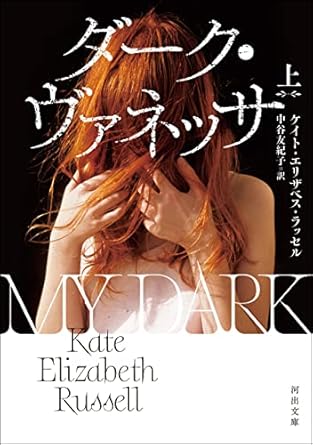
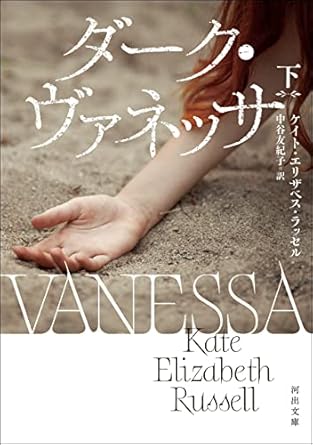
読んでて正直辛い。でも目が離せない。15歳の少女と42歳の教師の「恋愛関係」……と呼んでいいはずもない関係を、本人の目線から描いているんです。
「私は被害者じゃない、特別だった」と信じたいヴァネッサの気持ちが切なすぎる。現実の社会でも、告発を冷ややかに見る視線ってあるじゃないですか。そういうことを考えさせられる。
ただの“被害と加害”の話じゃなくて、心理の深いところをえぐってくる物語です。
『短くて恐ろしいフィルの時代』 ジョージ・ソーンダーズ 2021/8/5
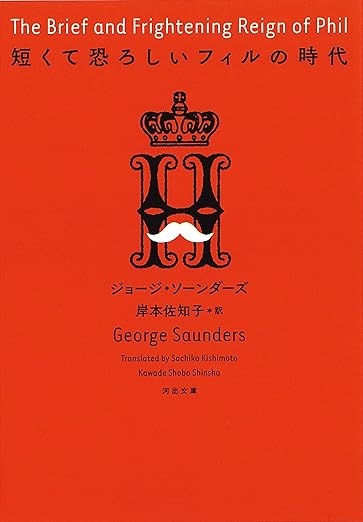
もう発想がぶっ飛んでます。脳が地面に転がるたびに演説で民衆を煽る独裁者……って何それ!? なんだけど、読んでいくとめちゃくちゃ寓話的で普遍的な話なんですよ。
独裁者のフィルは、たぶん誰の心の中にもいる。だから“またフィルの時代は繰り返される”かもしれない。この怖さ。
しかも文体が独特で、短いセンテンスでズバズバくる。笑えるんだけど、実際にはすごく恐ろしい現実の比喩でもある。これはクセになります。
『瞳の奥に』サラ・ピンバラ 2021/2/28
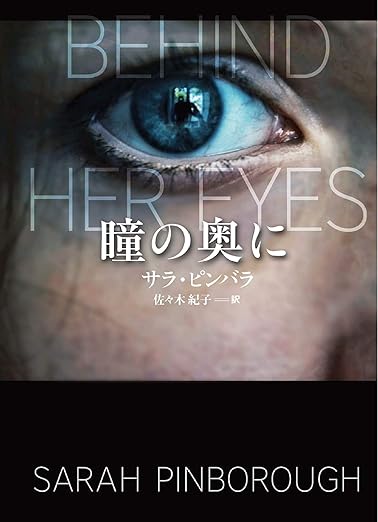
「結末は誰にも言わないでください」系の心理スリラー。序盤からドロドロの三角関係で「いやいやいや、その関係危険すぎるでしょ」って思いながらも、ページをめくる手が止まらない。
途中からヒロインが破滅に突き進むのが見えてきて、感情移入できなくなっても、それでも読むのをやめられない。
ラストまでたどり着いたら「ああ、だから“言うな”って言われてるんだ」と納得します。イヤミス嫌いでも楽しめちゃうかもしれません。
『ブルックリン・フォリーズ』ポール・オースター 2020/5/28
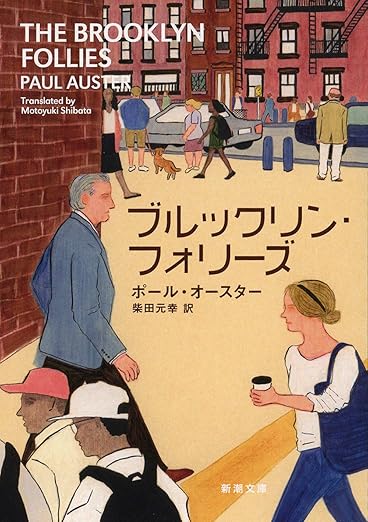
これはオースター作品の中でもめずらしく“晴れやかな読後感”が残る一冊。60歳で人生を諦めかけていた主人公が、ブルックリンに戻ってから人との出会いによって人生が転がっていく。
「奇跡って案外すぐそばにあるんだな」と思わせてくれるし、ジェンダーや政治、都会と田舎の格差なんかの要素も自然に織り込まれている。
オースターを初めて読む人にもおすすめできる、あったかい物語です。
『ジーヴズの事件簿 才智縦横の巻』P.G. ウッドハウス 2011/5/10
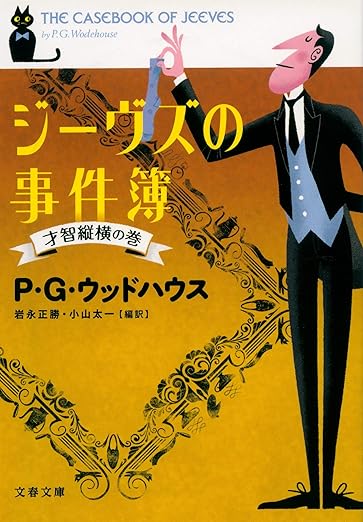
とんでもなく有能な執事・ジーヴズ。ご主人や周囲の人々がドジを踏みまくるんだけど、彼がサラッと解決していく。このパターンが気持ちいいんです。
事件が大規模だったりド派手だったりはしないんですが、会話のテンポがいいし、ジーヴズの皮肉混じりの知恵がクセになる。軽妙洒脱な英国ユーモアを楽しみたい人にぴったり。
『シェイクスピア&カンパニー書店の優しき日々』 ジェレミー・マーサー 2010/5/13
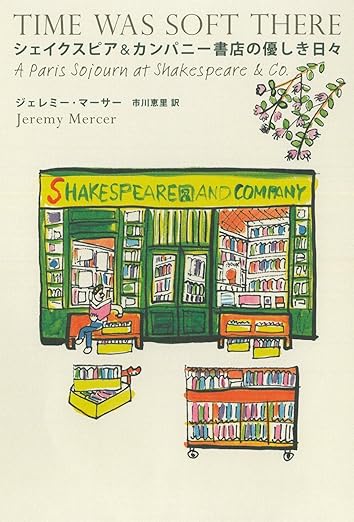
最後に紹介するのはちょっと変化球。本格ミステリじゃないけど「本好きなら一度は手に取りたい」一冊です。
セーヌ左岸の伝説的な書店で、作家たちや詩人たちが共同生活を送る。その記録なんですけど、とにかく“本への愛”が詰まっている。
ヘンリー・ミラーやギンズバーグ、ジョイスにヘミングウェイまで登場する。控えめで地味なんだけど、そこに確かに“文学の熱”があるんです。
絶版から復活したのも納得。これは宝物みたいな本です。
『ずっとお城で暮らしてる』シャーリィ・ジャクスン
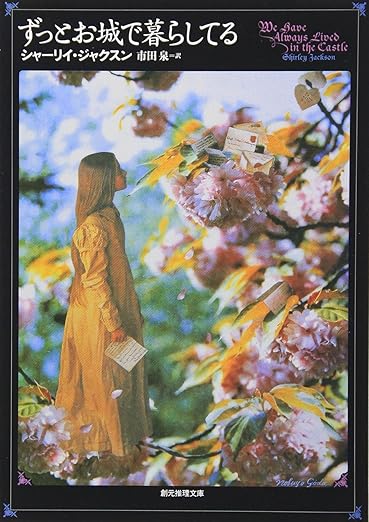
いやぁ……これがまたクセモノでした。メリキャットっていう少女の一人称で進むんですけど、彼女の語りがなんとも不気味。
一家毒殺事件の生き残りで、村人から忌み嫌われながら屋敷で暮らしてるんですよ。その日常がもう異様。彼女の「おまじない」とか「現実逃避」とかが混ざり合って、何が本当で何が妄想なのか分からなくなってくる。
読んでて「あ、この子、時が止まってるんだ」って気づいた瞬間、背筋がゾワッとしました。怖いんだけど、どこか切なくて……エンディングの余韻が忘れられません。
『愛のゆくえ』リチャード ブローティガン 2002/8/1
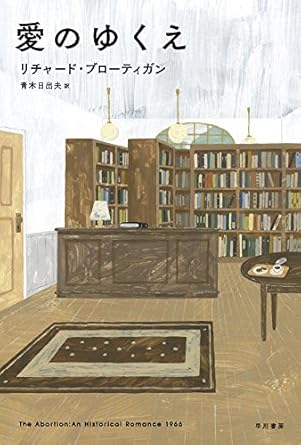
これは一見ラブストーリーなんだけど、ぜんぜん普通の恋愛小説じゃないです。風変わりな図書館に住み込む主人公が、完璧な美を持つヴァイダと出会い、関係を持ち、やがて妊娠。そして中絶を決意するんですが……描き方がすごいんです。
堕胎という重いテーマなのに、ドラマチックに盛り上げない。むしろ「アンチ・ドラマティック」「アンチ・ヒロイック」。淡々と、幻想的に、ちょっと内省的に。なのに胸に刺さる。
読んでいて「これは春樹だな」とピンとくる人も多いはず。実際、ブローティガンは吉行淳之介や大江健三郎、谷川俊太郎とも交流があったし、村上春樹が彼から強い影響を受けていることは明らかなんですよね。モチーフの選び方や人物描写の仕方に、その影が濃く出ている。
ラブストーリーとして読むと“淡い”。でも文学として読むと“濃い”。そんな二重の顔を持つ小説です。
ちょっと幻想に揺れるような文章を味わいたい人に、ぜひ手に取ってほしい。
まとめ
いやぁ……どれも心に残りましたね。謎解きにワクワクしたり、探偵のセリフにシビれたり、家族の葛藤に胸が痛んだり。海外文学ってやっぱりスケールが大きいし、テーマが深い。
「読んで良かった」って思える本は、読み終えた後も生活の中でふとした瞬間に思い出すんですよ。「あのシーン、なんか自分の人生にも繋がるなぁ」って。
もしあなたが次に読む本を探しているなら、このリストの中から気になる一冊を手に取ってみてください。夜中の2時までページをめくる覚悟は、必要ですけどね。


こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 心を揺さぶる 最強の海外本 を書きます。※本ページにはPRが含まれます