毎年恒例の「このミステリーがすごい!」ランキングの2025年版が発表されました。
本記事では、このランキングの概要と、注目すべき作品、そして今年の傾向について詳しく見ていきたいと思います。
対象となるのは2023年10月から2024年9月に刊行された新刊本です。ミステリーナビが詳しくまとめています。
- このミステリーがすごい! 2025版 発表!海外編注目作品と傾向
- 内容
- 1位:「両京十五日」馬伯庸(マー・ボーヨン)齊藤 正高 (翻訳), 泊 功 (翻訳)
- 2位:「ビリー・サマーズ」S・キング(著), 白石 朗 (翻訳)
- 3位:「死はすぐそばに」アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭訳
- 4位:「ボタニストの殺人(上下)」M・W・クレイヴン(著), 東野 さやか (翻訳)
- 5位:「ウナギの罠」ヤーン・エクストレム(著), 瑞木 さやこ (翻訳)
- 6位:「エイレングラフ弁護士の事件簿」L・ブロック(著), 田村 義進 (翻訳)
- 7位:「すべての罪は血を流す」S・A・コスビー/加賀山卓朗訳
- 8位:「魂に秩序を」マット・ラフ(著), 浜野 アキオ (翻訳)
- 9位:「ぼくの家族はみんな誰かを殺してる」ベンジャミン・スティーヴンソン/富永和子訳
- 10位:「身代りの女」シャロン・ボルトン (著), 川副 智子 (翻訳)
- 注目の作品分析
- まとめ
このミステリーがすごい! 2025版 発表!海外編注目作品と傾向
2025年版 海外ミステリーのランキング
「このミステリーがすごい!」は、宝島社が毎年発表している内外ミステリー小説のランキングです。ミステリー評論家や書店員など、専門家による投票で決定され、その年に出版されたミステリー作品の中から選ばれます。
今年の海外部門ランキングトップ10は以下の通りです:
| 順位 | 書名 | 著者名 |
|---|---|---|
| 1位 | 両京十五日 | 馬伯庸(マー・ボーヨン)、齊藤 正高 (翻訳)、泊 功 (翻訳) |
| 2位 | ビリー・サマーズ | S・キング、白石 朗 (翻訳) |
| 3位 | 死はすぐそばに | アンソニー・ホロヴィッツ、山田 蘭 (翻訳) |
| 4位 | ボタニストの殺人 (上下) | M・W・クレイヴン、東野 さやか (翻訳) |
| 5位 | ウナギの罠 | ヤーン・エクストレム、瑞木 さやこ (翻訳) |
| 6位 | エイレングラフ弁護士の事件簿 | L・ブロック、田村 義進 (翻訳) |
| 7位 | すべての罪は血を流す | S・A・コスビー、加賀山 卓朗 (翻訳) |
| 8位 | 魂に秩序を | マット・ラフ、浜野 アキオ (翻訳) |
| 9位 | ぼくの家族はみんな誰かを殺してる | ベンジャミン・スティーヴンソン、富永 和子 (翻訳) |
| 10位 | 身代りの女 | シャロン・ボルトン、川副 智子 (翻訳) |
内容
1位:「両京十五日」馬伯庸(マー・ボーヨン)齊藤 正高 (翻訳), 泊 功 (翻訳)

1425年北京から南京に遣わされた皇太子が主人公。宮廷の権力争いに巻き込まれ命を狙われる。北京の皇帝も命を狙われていると知った主人公は、役人や女医など一癖ある四人の力を借りて北京への帰還を目指す。タイムサスペンス。
2位:「ビリー・サマーズ」S・キング(著), 白石 朗 (翻訳)

3位:「死はすぐそばに」アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭訳

テムズ川沿いの高級住宅地リヴァービュー・クロースで、金融業界のやり手がクロスボウの矢を喉に突き立てられて殺された。昔の英国の村を思わせる敷地で住人たちが穏やかに暮らす――この理想的な環境を乱す新参者の被害者に、住人全員が我慢を重ねてきていた。誰もが動機を持っているといえる難事件を前にして、警察は探偵ホーソーンを招聘するが……。あらゆる期待を超えつづける〈ホーソーン&ホロヴィッツ〉シリーズ最新刊!
- 「本当に最新作が最高傑作の見本のような、大傑作でした!」「犯人当てミステリーの極致というしかない傑作!」【Web東京創元社マガジン 9月11日更新】
- ちょっと!!!あんた!!!ここで終わるって無いよ!!!!!続きは?続きは何年に出るの!?!?
- よくもまあ次から次へと古典ミステリを優良アップデートさせる発想があるなあと感心。
4位:「ボタニストの殺人(上下)」M・W・クレイヴン(著), 東野 さやか (翻訳)
5位:「ウナギの罠」ヤーン・エクストレム(著), 瑞木 さやこ (翻訳)
6位:「エイレングラフ弁護士の事件簿」L・ブロック(著), 田村 義進 (翻訳)
7位:「すべての罪は血を流す」S・A・コスビー/加賀山卓朗訳
8位:「魂に秩序を」マット・ラフ(著), 浜野 アキオ (翻訳)
9位:「ぼくの家族はみんな誰かを殺してる」ベンジャミン・スティーヴンソン/富永和子訳
10位:「身代りの女」シャロン・ボルトン (著), 川副 智子 (翻訳)
注目の作品分析
今年の1位に選ばれた『両京十五日』は、歴史的事実を基にした壮大なフィクションと、緻密なプロットが評価された点にあります。明王朝最盛期を舞台に、皇太子朱瞻基が15日間で2つの都を駆け抜ける緊迫の逃避行を描くこの作品は、政治的陰謀と個性豊かな登場人物の絡みが物語を彩ります。特に、史実を巧みに膨らませ、スリリングな展開と人間ドラマを織り交ぜた点が高く評価されました。
2025年版の傾向
「このミステリーがすごい!2025」海外部門では、歴史や文化的背景を生かした作品や、社会的テーマを盛り込んだミステリーが注目されました。多様な視点を持つ作家たちによる、緻密なプロットや斬新な語り口が評価され、特に歴史ミステリーや心理描写を伴う作品が上位にランクインしました。また、翻訳の質も選考の重要な要素となり、読者に原作の魅力をしっかり届けることが重視されています。
まとめ
読書愛好家の皆さんは、このランキングを参考に新しい作品との出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。

Amazonには「Amazonチャージ」というサービスが用意されています。この「Amazonギフト券 チャージタイプ」に現金でチャージすると、Amazonポイントが還元されるのがポイント。
例えば、プライム会員が現金で1度に10万円チャージすると、2,500円相当のAmazonポイントが貯まります。さらにプライム会員は通常会員よりも還元率が高くなります。
Amazonチャージを使って本を買うとポイントが還元された分だけ実質的な値引きになります。
Amazonギフトカード チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)
クレジットカードで決済するよりも、あらかじめ現金で「Amazonギフト券 チャージタイプ」でチャージしておく方がお得です。
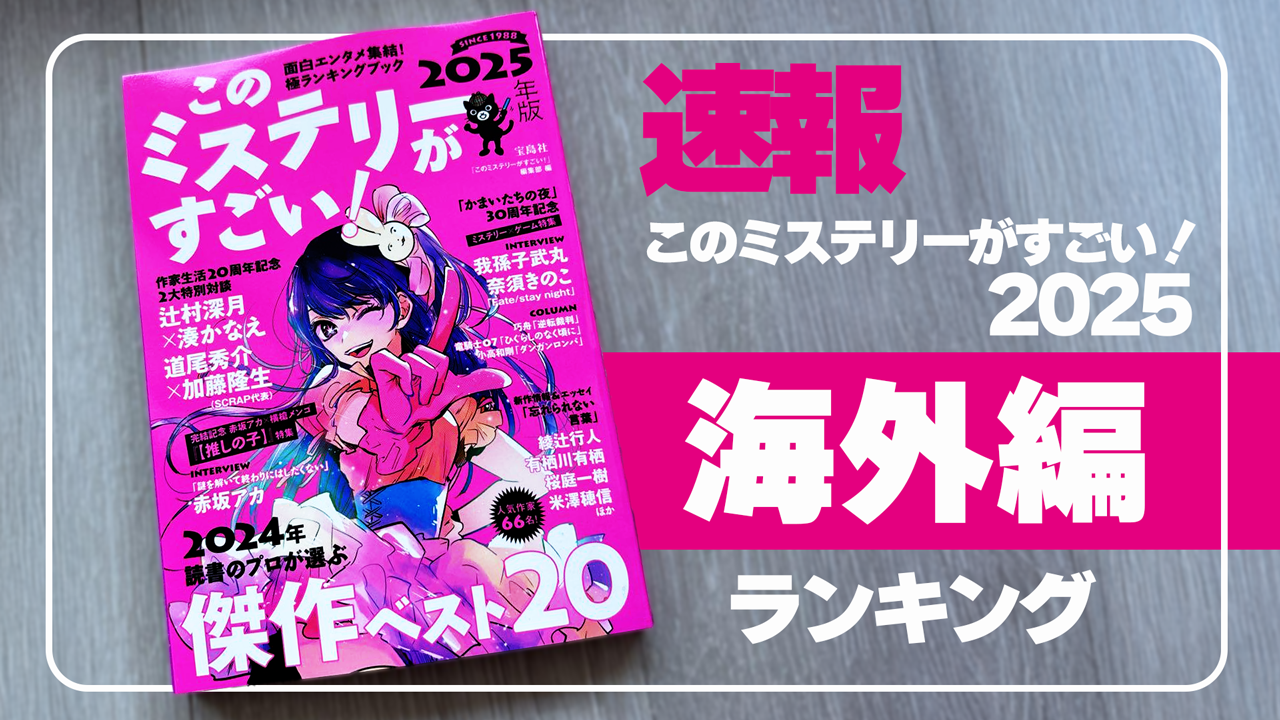




こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 このミステリーがすごい ! を書きます。※本ページにはPRが含まれます