このランキングは、怪奇幻想ライターで書評家の朝宮運河さんがX(旧Twitter)上で開催した企画で、多くのホラーファンが注目する内容です。怖いだけじゃない、心に残る作品が勢揃い。今回はランキングを眺めながら、国内編ホラーの得票を集めた作品にどんな魅力があるのか探ってみましょう!
ベストホラー2024 国内編ランキング
【拡散希望】今年もやります!!ホラー小説の年間ランキング企画「ベストホラー2024」をX上で開催いたします。あなたが今年読んで面白かったホラー小説を #ベストホラー2024 のタグとともに投稿してください。後日集計のうえベスト20までの結果を発表いたします。規定は下のリプ欄をご覧ください。→ pic.twitter.com/dTZfYve3QO
— 朝宮運河 (@Unga_Asamiya) December 13, 2024
🥇第1位:『深淵のテレパス』上條 一輝

ホラーとして娯楽小説として、非常に高いレベルでまとまっていた。――澤村伊智
息長く活躍してくれそうな期待を抱かせる、大器である。――東雅夫
両選考委員大絶賛の創元ホラー長編賞受賞作
見事1位に輝いたのは、上條一輝さんの『深淵のテレパス』。
会社の部下に誘われた大学のオカルト研究会のイベントで、とある怪談を聞いた日を境に高山カレンの日常は怪現象に蝕まれることとなる物語。読者の心をえぐるような心理描写と、想像を超えた恐怖の展開が話題に。まるで自分が「深淵」を覗き込んでいるような感覚に陥るそう。夜中に読むのは絶対にやめておきましょう!
🥈第2位:『極楽に至る忌門』芦花公園
四国の山奥にある小さな村には、昔から大切に祀られている石仏がある。東京から帰省する友人に付き添う隼人は、バスの中から異様な空気を感じていた。祖母の「頷き仏を近づけた」という言葉を聞くやいなや挙動不審になった友人は、その夜失踪する。そして隼人は悪夢に囚われていくー連綿と伝わる儀式とわらべ歌、3つの捧げ物、猿神信仰。最強の拝み屋・物部斉清も阻止できなかった土地の因縁と禍々しい怪異に戦慄する物語。
芦花公園さんの『極楽に至る忌門』が堂々の2位。「頷き仏」「泣き仏」「笑い仏」「外れ仏」の四つの章からなる長篇ホラー。タイトルからして怪しげな香りが漂いますね。登場する怪異の正体が明らかになるにつれ臨場感のある恐怖が楽しめます。芦花さん、ホラーランキングの常連らしいですよ。
🥉第3位:『眼下は昏い京王線です』芦花公園
大学生の琴葉は、飲み会の後にお持ち帰りされそうになっていたところを助けてくれたシマくんにひとめぼれする。すげないシマくんに振り向いてもらうため、彼が傾倒している「本当に障る話」の調査を手伝う琴葉だが、どうやら琴葉は霊や怪異を寄せる体質らしく、いつも命の危険があるような危険な目に遭ってしまう。
その度に大いに反省し、もうやめようと思うのだが、シマくんの素晴らしく良い声で誘われるとどうしても誘いを断ることが出来ないのだった――。ホラー小説界最注目の才能が放つ新感覚のエモーショナル・ホラー!
同じく芦花公園さんが3位にもランクイン!京王線の乗客には要注意!?この作品、実際に京王線沿線に住む人には刺さりすぎると噂とか。大切な存在を失った主人公の悲しみや絶望が心に響きます。ホラー好きな鉄道ファンにもオススメ!
第4位:『口に関するアンケート』背筋
肝試しに行った大学生達が、何が起きたのかをそれぞれ語る形式で話が進み、それぞれを繋ぎ合わせていく形でだんだん全体像が見えてくる。インタビュー形式で話が進むにつれて怖くなっていくホラー。
第5位:『みんなこわい話が大好き』尾八原 ジュージ
生き難い環境で暮らすひかり。ひかりの唯一の友だち・ナイナイ。押し入れに住むナイナイが行動を開始した時、ひかりの周りが劇的に改変されていく・・・。陰湿なイジメの主犯だったはずのありさが豹変し、ひかりの守護者に。
第6位:『穢れた聖地巡礼について』背筋
フリー編集者の小林が出版社に持ち込んだのは、心霊スポット突撃系YouTuberチャンイケこと、池田の『オカルトヤンキーch』のファンブック企画だった。
しかし、書籍化企画を通すには『オカルトヤンキーch』のチャンネル登録者数は心許ない。企画内容で勝負するべく、過去に動画で取り上げた心霊スポットの追加取材を行うことに。
池田と小林はネットなどで集めた情報をもとに、読者が喜びそうな考察をでっちあげていく――。
第7位:『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』寝舟 はやせ
実母のせいで貯金も住処も失ったタカヒロは、住み込みでマンションの一室を管理する仕事の求人を見つける。
雇用の条件は『隣人と必ず仲良くすること』。
他に行き場のないタカヒロはマンションに流れ着くが、待っていたのは明らかに人間ではない『隣人』だった。
「これは友達から聞いた話なんだけどね」
すでに23人が逃げ出したらしい部屋で、タカヒロはベランダ越しに怪談好きの隣人の話を聞くことに。
返答一つ間違えられない緊迫感の中、架空かと思われた怪談の内容は次第にタカヒロを取り巻く現実とリンクしていき――。
第8位:『右園死児報告』真島 文吉
右園死児案件が引き起こした現象の非公式調査報告書である。明治二十五年から続く政府、軍、捜査機関、探偵、一般人による非公式調査報告体系。右園死児という名の人物あるいは動物、無機物が規格外の現象の発端となることから、その原理の解明と対策を目的に発足した。
第9位:『さかさ星』貴志 祐介
呪われよ 子々孫々の果てるまで。戦国時代から続く名家・福森家の屋敷で起きた一家惨殺事件。死体はいずれも人間離れした凄惨な手口で破壊されており、屋敷には何かの儀式を行ったかのような痕跡が残されていた。福森家と親戚関係の中村亮太は、ある理由から霊能者の賀茂禮子と共に屋敷を訪れ、事件の調査を行うことになる。賀茂によれば、福森家が収集した名宝・名品の数々が実は恐るべき呪物であり、そのいずれか一つが事件を引き起こしたという。賀茂の話を信じきれない亮太だったが、呪物が巻き起こす超常的な事象を目にしたことで危機を感じ始める。さらに一家の生き残りの子供たちにも呪いの魔の手が……。一家を襲った真の呪物は? そして誰が何のために呪物を仕掛けたのか? 数百年続く「呪い」の恐怖を描く、待望の長編ホラー。
第10位(同率):『お前の死因にとびきりの恐怖を』梨
文芸部で発見されたUSBメモリ、新聞部の校内記事、合唱部の変遷レポート…etc.筆者がある高校から収集した、一見無関係な情報から浮き上がる”真実”とは。――これは青すぎるほど青い、とある「なけなしの救い」の物語。
第10位(同率):『撮ってはいけない家』矢樹 純
「その旧家の男子は皆、十二歳で命を落とす――」映像制作会社でディレクターとして働く杉田佑季は、プロデューサーの小隈好生から、モキュメンタリーホラーのプロットを託される。「家にまつわる呪い」のロケのため山梨の旧家で撮影を進める中、同僚で怪談好きのAD・阿南は、今回のフィクションの企画と現実の出来事とのおかしな共通点に気付いていく。そして現場でも子どもの失踪事件が起こり……。日本推理作家協会賞短編部門受賞『夫の骨』著者の最新作!
まとめ
今回のランキングは、単なる怖さだけではなく、人間心理や社会背景に迫る深いテーマを持つ作品が多い印象です。初めてホラーを読む人でも楽しめるものばかり。新しいホラー体験を求めて、ぜひランキング作品に挑戦してみてください!
朝宮運河さん
@Unga_Asamiya
怪奇幻想ライター・書評家 /インタビュー・書評・文庫解説などが主なお仕事/朝日新聞のブックサイト好書好日にて「朝宮運河のホラーワールド渉猟」連載中 /編纂アンソロジーに『家が呼ぶ』『宿で死ぬ』『再生』『恐怖』『影牢』『七つのカップ』/編著に児童書版『てのひら怪談』/ランキング企画 #ベストホラー2024 運営です
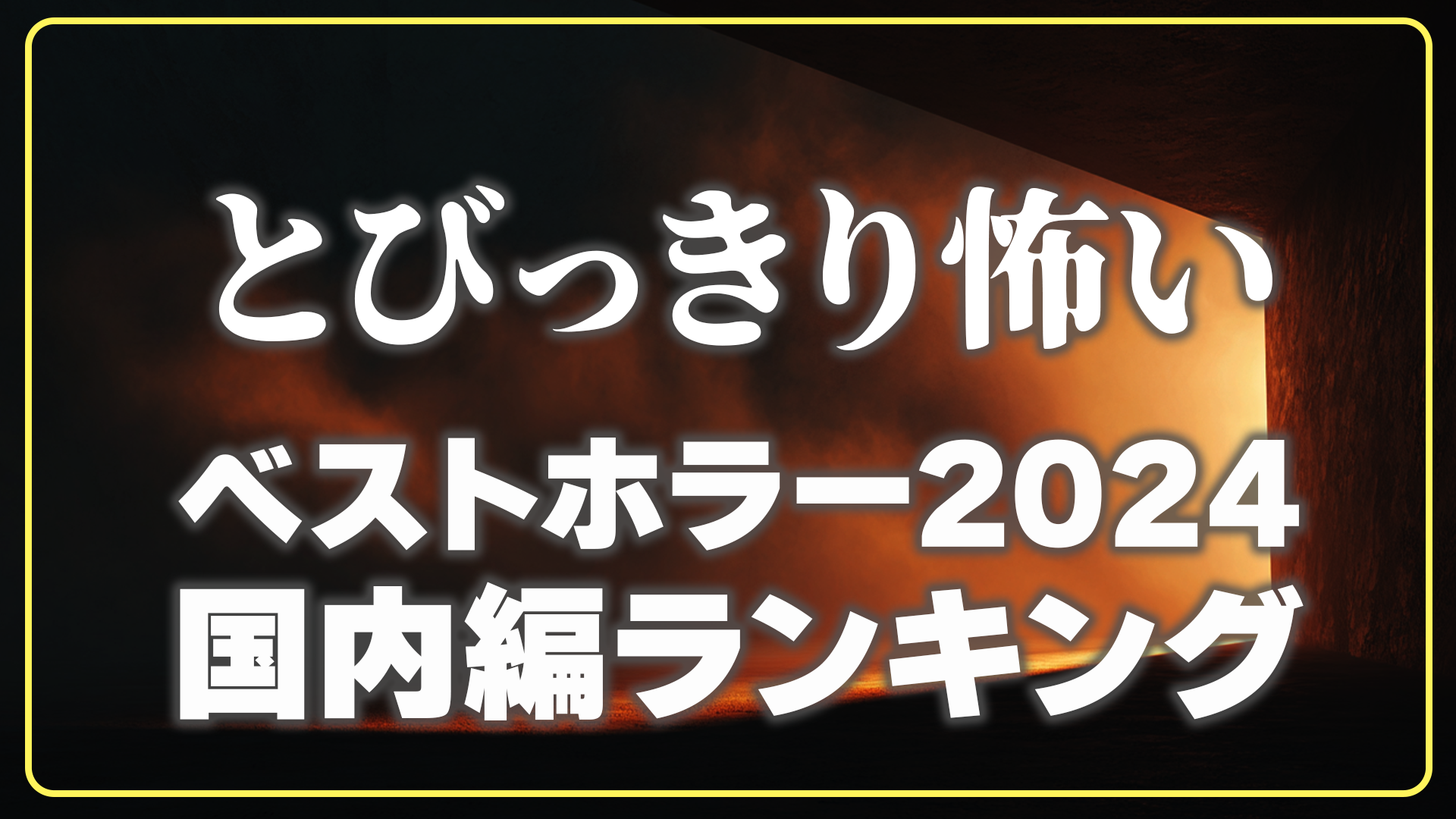



こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 今日はホラー好き必見の「 ベストホラー2024 」国内編ランキングをご紹介します。※本ページにはPRが含まれます